風土を決定する要因は数えきれないが、風土という文字が示すように「風」と「土」が主要因になりそうだ。食は風土によって決定される。人類は好きなものを食べてきたのではなく、風土に育まれた食材を口に運んだ。環境に食性を決定されてきた。今は何でもありになったのでこのことを忘れがちだが、われわれの祖先は日々ほぼ同じものを――好きとか嫌いとかつべこべ言わずに――繰り返し糧にしてきたのである。
〃
何度同じことを言い、同じことを書いてきたことか。そうこうしているうちに、言語は脳で記憶するだけでなく、身体、とりわけ筋肉と同化する。母語も外国語も反復によって習熟度が高くなる。只管朗読、只管筆記、侮るべからず。
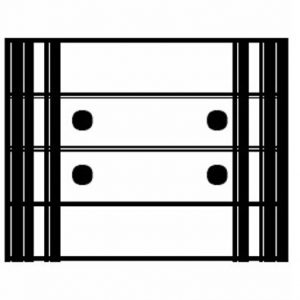
〃
来年2月に本ブログは1,500回に達する見込み。約11年半、月平均10回、1回の記事は原稿用紙に換算すると平均3、4枚。特別な才能も大いなる努力もいらない。ある種惰性のような執拗さとただひたすら繰り返すことだけが求められる。
〃
繰り返し(あるいは反復)はマンネリズムと安心(あるいは油断)を生む。いちいち考えなくてもよくなる。同時に、ある事柄に精通し、熟練度が進む。功罪相半ばする。さあ、どうしたものだろう。
〃
反復しながらも、意識的に何かを少し変えてみると、いつもの景色が少し変わる。昨日と違う緊張感と新鮮味が出てくることがある。飽き性の凝り性だからそこに期待するしかない。ここ10日間ほど、どちらかと言えば機械的な作業をずっとやってきた。最初は愚痴をこぼしながらやっていたが、完了間際にして楽しんでいることに気づいた。仕事は……たとえそれがマンネリズムに満ちることがあっても、選んだ以上は楽しむに限るのである。








