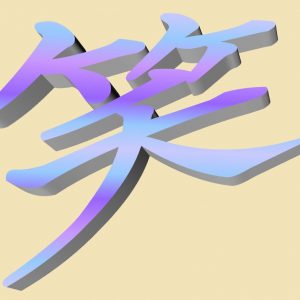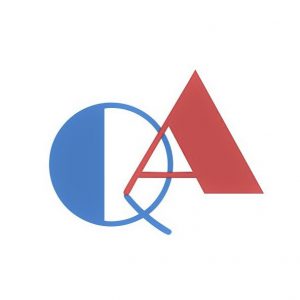🖋 雨が降っている時の雨音はまったく気にならない。雨が止んだ後に軒から物置の上に落ちてくる滴の音はかなり気になる。
🖋 コメントが付いていないシェアは体裁のいい盗作。
🖋 「立派な趣味ですねぇ」「いやあ、ほんのままごとですよ」……本人はままごとなどと絶対に思っていない。
🖋 「考えることだけが唯一の希望だ」とジョージ・オーウェルは言ったが、希望のない人はそもそも考えようとしない。
🖋 エイジングが進んでいるのか、アンチエイジングできているのか……医者よりも歯と筋肉に直接聞いてみるのがよい。
🖋 嘘をつかないK氏のつぶやき。
「寒いなあ」と思ったら窓が開いていたんですよ。翌日、「昨日よりさらに寒いなあ」と思ったら、窓が開いていたうえに素っ裸だったんですよ。
🖋 手をまったく汚さずに万年筆のインクを充填できたことは一度もない。
🖋 「また飲みに行きましょう」とシニアが言う時、指先をお猪口の形にして口に近づける。ビールかハイボールしか飲まない人でもそうする。
🖋 以前豪ドルを買ったが、豪ドル紙幣は見たことがない。今日、銀行で金の積立預金を始めたが、金貨も金の延べ棒も契約期間中に見ることはないだろう。
🖋 その銀行で各種粗品セットをもらった。ティッシュも入っていたが、商談デスクの上に置いてあった印鑑拭きが欲しかった。
🖋 お笑い芸人の「いつもここから」の山田一成の『やまだ眼』を古本屋の店先で見つけた。金百円也。「電車の弱冷房車に不良が乗っていた」という観察が微妙に可笑しい。