演説とは英語にて「スピイチ」と言い、大勢の人を会して説を述べ、席上にて我思うところを人に伝うるの法なり。我国には古よりその法あるを聞かず、(……) 西洋諸国にては演説の法最も盛んにして、(……)僅かに十数名の人を会することあれば、必ずその会につき、或いは会したる趣意を述べ、或いは人々平生の持論を吐き、或いは即席の思付を説きて、衆客に披露するの風なり。
福沢諭吉『学問のすゝめ』十二編、演説の法を勧むるの説の冒頭である。考えることを他人に伝えるのが演説であり、演説にはルーチンがあると教えている。わが国には存在せず、西洋では常識の弁論術はさぞかし当時は新鮮だったに違いない。これ以来、日本では弁論とはスピーチのこととなった。今もそう捉えられている。正しくは、討論や対話も弁論である。
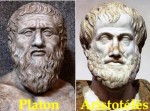
プラトンは「正しいことを思いなしているのに、それを説明できないのはほんとうに知っていることにならない」と『饗宴』の中で語っている。説明とは説得であり証明である。分かっていることなのに、聴衆にアピールできないほどもどかしいことはない。弁論の最終目的は「自分が分かる」ことではなく、「聴衆が分かる」ことである。聴衆が話を聞いて賛成か反対かを決める。聴衆はどのように弁論者によって説得されるのか。プラトンの弟子アリストテレスは言う、「説得は一種の証明である。人は何かが証明されたと感じるとき、よく説得される」(『弁論術』)。そして、三種類の説得立証を明らかにした。
1.事柄のロゴス、つまり論理的説明に対する納得
2.語り手のエトス、つまり品性・人柄を通じての信用
3.聴衆のパトス、つまり感情を通じての共感と同意
説得立証のうち、下記の例のような、前提から結論を導くものを説得推論と呼ぶ。
前提1(論拠) 「デパートでバーゲンすれば女性客が増える」(真偽不明)
前提2(証拠) 「今日は女性客がいつもと同じ入りである」(一応真としておく)
結論 「ゆえに、今日はバーゲンを実施していない」(真偽不明)
前提があやふやで、結論の蓋然性も定まらないが、この推論は〈PならばQ、だがQではない。ゆえにPではない〉という妥当な推論形式に従っている。変な言い方になるが、真偽のほどは明らかになっていないけれども、この推論は論理的である。そして、論理的であるということは、説得にあたっての基本条件を一つクリアしていることになる。
推論は、一つまたは複数の前提から結論を導き出す。妥当な形式の推論をおこなえば、前提が真ならば必ず結論も真になる。たとえば、「ホッチキスは文房具である(真)。文房具は事務用品である(真)。ゆえにホッチキスは事務用品である(真)」という具合。真である前提からは真である結論が導かれる。こんなことはくどくどと推論しなくても分かる。にもかかわらず、論理的であるためには、わかりきった事実をしつこく積み重ねていかねばならない。無意味な回りくどさや無駄口は避けるべきだが、推論作業で手を抜くことはできない。
〈帰納〉という推理がある。帰納は複数の個別命題から一つの普遍命題を導く。「太郎はよく遅刻する」「太郎は時間にルーズである」「太郎は忘れ物をする」という三つの前提から「太郎は信頼性に乏しい」という一つに括った結論を導くようなケース。ところが、個別命題が三つとも真であっても結論の妥当性は確定しない。個別で小さな情報から普遍で大きな概念に仕立て上げるには膨大な情報が必要で、数例によって推論するのは妥当ではない。したがって、この場合、太郎に貼られたラベルが真である保障はない。但し、討論や実社会の意思決定の常として、妥当性の検証や命題への反証を怠ると、偽であるかもしれない普遍命題が成立してしまう。
弁論において論証力を高めようと思えば、具体的で確かな例証と「真実に近いもの」を示す蓋然命題を豊富に携えることである。いわゆる共通感覚に根ざしたものの見方や教養だ。「他人を妬む人は他人を憎むようになる」や「借りたものは返却すべきである」や「子どもは躾けるべきである」などの命題は、安易な反証・反例をシャットアウトし、したがって相手もおおむね認めざるをえない理屈を備えている。否定できないわけではないが、否定すれば聴衆や世論を敵に回しかねない。
最強の共通感覚になりうるのは究極の最高善である。アリストテレスはそれを「幸福」とした。幸福こそ万人に共通の、蹂躪しがたい善である。なぜなら、たいていのことには「なぜ?」と問えるが、「なぜ幸福が重要なのか?」などと異議申し立てるのは不可能だからである。