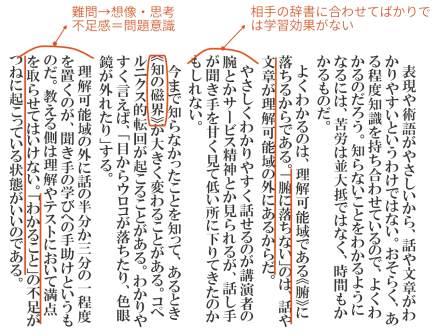知り合いか自分のどちらかが、この男たちに対応されていたらと思うとぞっとする。「顧客の立場から考え振る舞う」などとキレイごとを教えても、無意識世界の人間の本性は変わらないし変えることができないかもしれない。そんな絶望感に襲われる。
日曜日の昼下がり、とある商店街で買物を済ませ帰路についていた。その商店街に何度か通った整形外科がある(美容整形ではない)。そこからわずか20メートル、交差点角の調剤薬局で薬をもらったのを思い出す。見れば、その薬局はない。そこは賃貸住宅の営業所になっていた。外からよく見えるガラス張りでスタッフが数名いる。交差点で信号待ちしていると、そこから男性スタッフが二人出てきた。ランチに出掛ける様子だ。
信号を渡る。彼らはぼくのすぐ右前を急ぎ足で歩く。二人のうち年上の三十代半ばのほうが、向こうから歩いてきた若い男に声を掛けた。「さっきの親子、どうやった?」 若い男は照れるように首を横に振り、左右の手でバツのジェスチャーをした。「何しとんねん、捕まんかい!」と年上の男。ぼくの前をさらに急ぎ、男二人は商店街から脇道にそれ大衆食堂に入った。不況忍び寄る不動産業界よ、「何言うとんねん、誠意見せんかい!」
壁に耳あり障子に目あり。耳と目は壁や障子の向こう側だけにあるとはかぎらない。顧客の耳と目はそこらじゅうにある。耳と目はぼうっとしていることも多いが、ここぞというときには聞き耳を立て目を凝らす。そのことに気づいていない売り手はやがて二枚舌を暴かれ、表と裏、ホンネとタテマエ、天使と悪魔のいずれであるかを見破られる。
通りの角をお客が曲がって消えるまで見送り続ける料亭の女将。見送り届けた直後のことば遣いを聞き、表情を見てみたい。そこに落差ありやなしや。あるとすればどんな落差か。上客におべっかを使ったと思えば、帰った客の金遣いの悪さにチェッと舌打ち。従業員の不手際を怒鳴り散らした直後に、ささやくような声で平身低頭で詫びを入れる。
電話中と電話を切った直後の態度とことばの落差。得意先訪問中と社屋を後にした直後の態度とことばの落差。講演直後には褒めちぎられたものの、パスした懇親会でボロクソの欠席裁判。時々そんな悪夢を見る。だいたいにおいて、異様なほど過分に褒められているなと感じたときは、褒めた連中が陰に回ってから悪口を楽しむだろうと推察していい。
ある駅に降り立った。徒歩10分ほどの位置にあるホテルがよくわからない。駅前にある賃貸オフィスは、接客中でないにもかかわらず、場所を尋ねるぼくに「知らない」と軽くあしらった。その土地の顧客になりえない出張族への接し方一つで人と店の質がわかる。真剣にこちらが対峙すれば、粉飾された束の間の誠意を見破るのはさほど難しくない。ふだんの習性は、たとえ必死にカモフラージュしても、ことば遣いと立ち居振る舞いに滲み出るものだ。
舞台の上と楽屋での言動を完全一致させることはないし、そんなことは無理な話だろう。しかし、感謝や誠意や親切などは「時と場合に応じて」というものではない。「精神的お辞儀の角度」は表でも裏でも同じだからこそ尊いのだ。営業スタッフよ、むくれた顔になりたくなければ、即刻仮面を外したまえ。
「よく言うよ、あんただって他人批判をよくしているじゃないか」という声が聞こえてきそうだ。たしかにぼくも本人のいないところで毒舌を吐く。しかし、本人がいるところでも同じように毒舌を吐く。相手が無理難題を突きつけてきたとする。泣く泣く持ち帰って陰で悪態をつかない。その場ではっきりと自論を述べる。若い頃は他人の仮面を剥がそうとしてできず、よく失望した。ここ数年は自分自身の仮面と闘っている。仮面は他人に向けられた詐術だが、欺かれる第一の犠牲者は自分自身である。