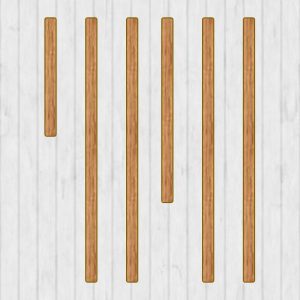住所と立地、場所と景観、地域と歴史などについて、依頼されてコラムを書いている。一編をだいたい500~600字でまとめる。ここ半月ばかり一日二編のペースだが、書くほどに〈場〉という概念が気になる。名称で示される場もそうだが、トポス的な〈ありか〉という意味についても考えさせられる。
都道府県、市区町村、丁目番地号などの名称と数字を見れば、〈ありか〉はピンポイントで判明するが、このアドレスからは場の特徴、周辺環境、さらには歴史的沿革やエピソードなどの情報はわからない。「わらび餅のうまい店がある」とか「自民党支持者が多い」などという情報は――もし知りたければ――アドレス以外の情報を調べるしかない。その気になれば、Googleだけでほぼ何でも検索でき、ほぼある程度のことがわかる。
「何を言ってる? 地名から由来がある程度わかるではないか」と言うむきもあるが、いやいや、地名からは生半可な類推しかできない。地名に「川」が含まれていても川があるとはかぎらないし、「江」が含まれていても海や湾が近くにあるとはかぎらない。「津」を含む地名は大昔が海だったというケースがほとんどで、今は海から遠く離れた高台にあって、津よりはむしろ丘と呼ぶにふさわしかったりする。
町名に「湯」を含んだまちに住んだことがあるが、湯は湧き出していなかった。銭湯はあったが、銭湯があるからと言っていちいち「湯」をつけるはずがない。そんなことをすれば、日本全国、「湯」のみならず、「酒」「米」「魚」のつく地名が溢れる。酒屋も米屋も魚屋もどこにでもあるのだから。今住む町には「泉」がつくが、あたりに泉は湧いておらず、泉の広場も見当たらない。但し、文献をひも解けば、一千年前までは泉が湧いていたなどという事実に突き当たる可能性はある。しかし、それはアドレスからわかる事実ではない。
家やマンションを買ったり借りたりする、あるいはどこかに旅してホテルやアパートに泊まる。住まいや行き先のアドレスは、だいたいではなく〈ありか〉がわかるように表記されていなければならない。しかし、実際のところ、ぼくたちの関心は、築何年とか間取りとかエクステリアの様子とかに始まり、大まかな〈場〉のステータスや評判、周辺環境やアクセスに至るまでの、アドレスにはない情報に向けられる。中心点としてのアドレスよりも周縁のほうが意味を持つ。歴史やエピソードは周縁的情報の類だ。
ところで、アドレスには、日本のように「県、市、区、町、丁目番地」と大概念から小概念へと降順的に並べる型と、アメリカのように「番地、町、市や群、州」と小概念から大概念へと昇順的に並べる型がある。前者には〈ありか〉の的を絞っていくプロセスが窺え、後者には〈ありか〉から始まってそれを定義していくプロセスが感じられる。今日のところはこれ以上深入りしないが、アイデンティティや帰属に対する考え方の違いだと思っている。