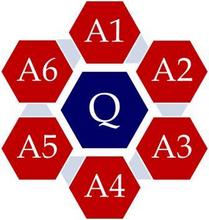きみは真鍮の溝の上に左足を置き、右肩で扉を横にすこし押してみるがうまく開かない。
ミシェル・ビュトールの『心変わり』はこのように始まる。そして、次のように終わる。
通路にはだれもいない。きみはプラットホームの群衆を眺める。きみは車室を離れる。
この小説のあらすじをここに書くつもりはない。もっとも、ぼくが読んだのは三十数年前で、あらすじを書けるほど覚えてもいない。パリからローマへと一人旅する男の列車内における観察と描写は執拗であり細部に及んでいる。話よりもそのことが強く印象に残っている。
主人公が「おれ」や「ぼく」や「わたし」などと一人称代名詞で語っているなら、読者は他者として状況や物語を感じ取ることができる。また、「彼」や「彼女」と三人称であれば、読者と主人公の距離は少し広がって客観する立場が強まるかもしれない。ところが、この小説は二人称代名詞の「きみ」で綴られ、それによって注目を集め話題になった。
「おれは昨晩度を越すほど酒を飲み、翌朝ひどい頭痛に悩まされた」と書かれていても、「あ、そう」と読者は平然と読めばいい。ところが、「きみは昨晩度を越すほど酒を飲み、翌朝ひどい頭痛に悩まされた」と作者が綴れば、読者は否応なしに当事者へと変身させられてしまう。読者であるはずのぼくが、「きみ」という二人称の語りを読み進めるにつれ、作品の中へ主人公として引き込まれてしまうのである。
「その日、きみは午前七時に起床して、近所の喫茶店でモーニングを注文した」と書かれると、行動が観察されたことになる。いや、このように事実を語られるだけならまだ冷静でいられる。しかし、「きみはトーストの端っこを齧り、バターの味が薄いことに若干の不満を覚えた。むろん、そんなことできみは腹を立てたりなどしない。コーヒーをすすってトーストを流し込んでしまえば別にいいさ、ときみは思う」となると、話は別である。心象や心理まで描かれたら、すべてを見透かされた気分にならざるをえない。「いや、違う。ぼくはそんなふうに思ったりしていない」と反撥しても、書き手は一切聞く耳を持たず、「きみ」を主語にして話を進めていく。
誰が語っているのか、誰が思い行為しているのかが明示されなければ、文章で語られていることは空疎なのだ。再び『心変わり』の一節。誰がそうしているのかがわからないように主語を伏せてみた。どうだろう。なんとなく落ち着かず、「いったい誰が?」と問いたくなる。
扉から頭をつきだし、左右を眺め、車室をまちがえたのに気がつき、遠ざかり、見えなくなる。
この主語が「きみ」なら事件だが……。実際の文章は次のように書かれている。
ひとりの男が扉から頭をつきだし、左右を眺め、車室をまちがえたのに気がつき、遠ざかり、見えなくなる。
文は個々の単語の組み合わせで意味を持つ。しかし、それ以上に重要なのは「主述関係」という構造なのだ。主語の人称が変わると主語と述語の関係が変わり、ひいては意味や気分が変わり、そしてたぶん、思考軸までもが変わるのである。