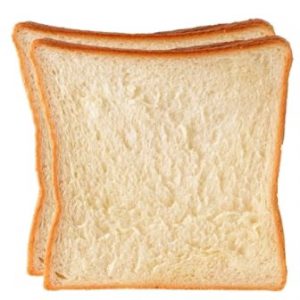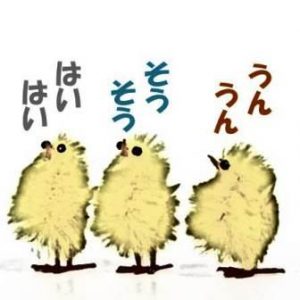いろんなことを実によく考えるものだ。あの手この手。他人の創作にある時は呆れ、またある時は感心する。仕事柄ことばの言い回しに工夫をしなければならないので、自分でも創作する。愉快とリズムをなるべく意識するようにしている。
繁華街の入口に看板が出ている。「即日体入高収入」。人材募集らしきこと、少々怪しげな職種であることを感知する。体入とは体験入店。試しにその日にバイトを始めればその日から稼げるというメッセージである。
今度の台風は強いぞ、大きいぞ。被害甚大に気を付けよ。進路予想を見ればわが街も直撃エリアに該当している。ところが、いつ通過したのかもわからないほど、あっけないことがある。決死の覚悟をしていたのに、通常の雨の日とほとんど変わらない。被害地には申し訳ないが、ぼくは「がっかり台風」と呼んでいる。
「モダンは追う。流行は追わない」(フォルクスワーゲン)
これをもじった自作のパロディがある。
「安いワインは飲む。安っぽいワインは飲まない」(岡野勝志)
人は自己を誇示したり正当化したり言い訳したりするためにキャッチコピーを作る。
町内の釣鐘が時を告げる。ゴーン、ゴーン。その鐘の音を耳にするたび思い出す。
ゴーンゴーンとすり寄って保身した者たちはいまどこで何してる (岡野勝志)
四字熟語で攻める。
「放蕩三昧の勇気なく、無為徒食にも居直れず。日々の刻苦精励も及ばず。おおむね中途半端に生き長らえていく」(岡野勝志)
カタカナの漢字変換。分厚いハンバーグのことを「味覚認肥厚物体」という。前日に仕込んだのを焼いてしかと存在を確認し、しかる後に消滅させることに成功した。