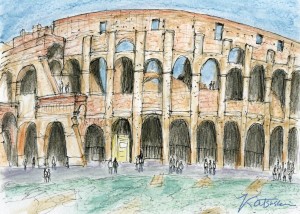「落し物」とタイトルに書いたが、実際に落としたのかどうかわからない。どこかに置き忘れたのかもしれない。失ったかもしれないが、また出てくるなら、どこかに潜んでいるはず。いずれにしても、「それ」はぼくの手元から消えた。食事も喉を通らず、仕事も手に付かずという落ち込みようではないが、少し残念な気分である。めったにモノを失くさないぼくなのに、今年は夏場にも愛用の万年筆の一本を紛失している。見返りの拾い物は、今のところ、ない。
失くしたのは小銭入れだ。買った当時は紺色だったが、数年間使いこんでいたので色合いは黒に近い。円安の現在よりもさらに円安だった頃に30ユーロで買った。当時の円で5,000円くらい。まあ、金額のことはどうでもいい。実はこの小銭入れは二代目であり、茶色の初代は古物ケースの中に今も入っている。
何事に関しても、あまり残念がらない性質だが、少なからず残念がっている。小銭と折りたたんだ千円札が一枚入っていたからではない。なぜ残念な落し物かと言えば、ささやかな思い出も入っていたからである。
フィレンツェにはアルノ川が流れている。あまりにも有名なポンテヴェッキオはそこに架かる橋だ。そのポンテヴェッキオから北側へ少し歩いた所にソニアという店がある。2007年3月、ぼくはフィレンツェの南岸のアパートに3泊、シニョリーア広場に面したホテルに4泊した。街の隅々を歩き、おそらく十数軒の料理店に足を運んだ。
フィレンツェには2003年にも4泊した。めったに土産物に目をくれないが、ソニアで初代にあたる茶色の小銭入れを買った。この財布は一枚皮でできていて、丸みのある細工を凝らしてある。よく似た小銭入れは日本でも売られているが、仕上がりに不満があり、しかも1万円以上するものばかりである。初代をとても気に入って4年間愛用した。丈夫な代物だが、さすがに色褪せてきた。ところで、ぼくの初代を見た知人やスタッフが自分にも買ってきてくれということになり、色の好みを聞いて十数個の注文を引き受けた。その際に買ったのがこの二代目だった。
かなりの数の商品を買うのだから、ソニアでかなり長い時間をかけて品定めをした。店主である老婦人ともイタリア語で親しく会話を交わし値段交渉もした。しかし、これだけ大量に買うというのに1ユーロもまけてくれなかった。落胆したぼくを見て「値引きはしないけれど、サービスでつけておくわ」と言って差し出してくれたのが、皮の名刺入れと付箋紙ケースであった。名刺入れは人にあげたが、付箋紙ケースは今も使っている。
大袈裟に言えば、写真やメモやガイドブックとは別の「回想の形」になってくれていたというわけだ。小銭入れをポケットから出し入れするたびに、ちょっとしたフィレンツェ気分を味わっていたのである。二代目を失くした数日後に先代の小銭入れを手に取ってみたが、現役に復活させるのは忍び難い。というわけで、使いにくいアメリカ製の小銭入れで済ませている今日この頃である。