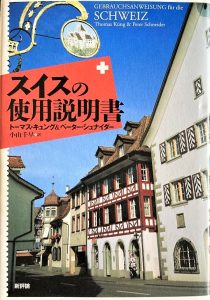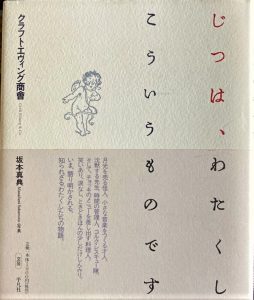よく観察もせずに「季節が移ろう」などと感覚だけでつぶやく。季節が変わろうとしてなかなか変わり切らず、寒さが戻ったと思うと再び温かくなる。これを数回繰り返すこの時期は、毎日毎日が微妙に移ろう。対象を接写的に見ればそのことに気づく。日々流されて生活していると気づかないが、しばし立ち止まることがなかなかできない。
日曜日に園芸店で旭山桜(別名、一才桜)の小さな鉢植えを買い、昨日オフィスに持ってきた。今朝つぼみが赤らんでいた。4月中旬から5月中旬が咲き頃と聞いたが、園芸店では早く咲かないようにたぶん温度調整している。オフィスは園芸店よりも陽射しがよくて暖かいから、早めに開花モードに入ったのかもしれない。
移ろうのは季節ばかりではない。この2年、コロナとウクライナという、人生史上の大きな環境変化に飲み込まれて、これまで確固としていたはずの考えが変わっていたり思いが容易に揺らいだりしていることに気づく。
たとえば「やればできる!」 この励ましは、人を励ますどころか失望させる、けしけらん言い方だと思ってきた。結果としてできなかったら、「きみ、やっていなかったからだよ」と助言者は逃げることができる……欺瞞だ、幻想だ、無責任なひどいことばなどとこきおろしてきた。ところが、この考えが変わったのである。「やってもできないかもしれないが、やっている間は少なくとも怠け者にならずに済むのではないか」と今は思っている。意識的に凡事のルーチンを毎朝しているうちに、ぼくも少しは勤勉になった気がする。そして今、「やればできる!」と言いそうになっている。
「もうちょっとの辛抱だから」という慰めも無責任だと思っていた。「もうちょっと」がいつまでのどの程度の辛抱かよくわからないじゃないか、全然慰めになっていないぞと文句を言った。そうは言うものの、それ以外に選択肢が見当たらない時があることに最近気づくようになった。小さなことをマメに続けることが「もうちょっとの辛抱」なのかもしれない。明日になったらどうする? 「ほんの少しもうちょっとの辛抱」をすればいい。毎日そう自分に言い聞かせることが、あながち空しいことだと思わなくなった。
自分の考えや思いが移ろいつつあることに気づき、そのことを受け入れるようになる時、発想のこわばりとこだわりがほぐされて、ほんの少しだけものがよく見えるような気がする。