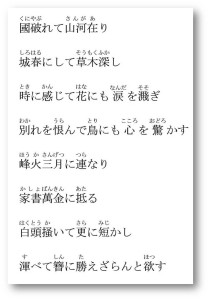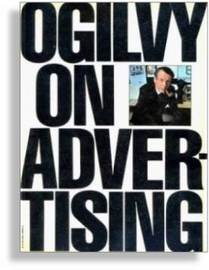企画業のかたわら、三十代後半から人前で話をさせていただいてきた。「浅学菲才の身」という、心にもないへりくだりはしないが、我流の雑学しかやってこなかったから、知識の出所についてはきわめてアバウトである。しかし、そうだったからこそ、思うところを語れてきたし、二千回を超える講演や研修の機会にも恵まれて今日に到ることができた。学者の方々には申し訳ないけれど、つくづく学者にならなくてよかったと思っている。
企画業のかたわら、三十代後半から人前で話をさせていただいてきた。「浅学菲才の身」という、心にもないへりくだりはしないが、我流の雑学しかやってこなかったから、知識の出所についてはきわめてアバウトである。しかし、そうだったからこそ、思うところを語れてきたし、二千回を超える講演や研修の機会にも恵まれて今日に到ることができた。学者の方々には申し訳ないけれど、つくづく学者にならなくてよかったと思っている。
学者にあってぼくにないものは専門性である。深掘りが苦手だ。その欠点を補うために異種のジャンルを繋げることに意を注いできた。これには、新しい問題の新しい解決を目指す企画という仕事を志してきた影響が少なからずあっただろう。何よりも、奔放にいろいろなテーマに挑めてきたのは、個々の精度にとらわれず、学んだことをうろ覚えながらもアウトプットしてきたからだ。もちろん、そんなぼくでも読んだ本を極力正確にノートに引用してきたし、観察したことや見聞きした事実などは固有名詞を踏まえてメモしてきた。それでもなお、うろ覚えの知識もおびただしい。だが、確かな知からうろ覚えの知を引き算していたら、生涯書いたり話したりなどできないと腹をくくった。
学者は、参考文献の出所や出典を明らかにして、該当箇所を正しく引用することを求められる。引用間違いをしたり書き写し間違いをしたりすると困ったことになる。引用符内の文章を故意に歪めてはならず、また、故意でなくても誤って間違うとみっともないことになってしまう。どの文献だったか忘れてしまったときに「たしか」では済まされないのだ。これにひきかえ、ぼくなどは立場が気楽である。デカルトにいちゃもんをつけた哲学者ヴィーコよろしく、身勝手に「真らしきもの」をおおよそ真として語ることができる。今こうしているように、書くこともできる。
納得できない人もいるだろうが、さらに批判を覚悟の上で書こう。
「ぼくの経験」を語ることの信憑性と、「たしかこんな本に次のようなことが書いてあった」という信憑性にどれほどの違いがあるのか。学術的には精度が低くても、聞き手に伝えたいこと、教訓として知っておいてほしいことがある。まったくでたらめなフィクションではないが、経験であったりうろ覚えであったりする。それをぼくはネタにしてきた。精度を重んじるあまり、口を閉ざすにはもったいない話はいくらでもあるのだ。間違いかもしれない引用、あるいは読み間違いや聞き間違い、場合によっては勘違いかもしれない。しかし、「それらしきこと」や「見聞きして覚えていること」を話さないのは機会損失である。
何かの本で読んだことは間違いない。ある程度話を覚えもしている。その本は探せば書棚のどこかにあるはずだ。学者はその本を探し当てて正確に引用せねばならない。しかし、ぼくはおおよその記憶を頼りにいちはやく話し始める。
「理髪店に行くと、何かが変わる」という一文を読んだことがある。たしか、「まずヘアスタイルが変わり気分が変わる」ようなことが書いてあった。そして、「もしかすると、魂が変わり、ひょっとすると、髪型だけではなく顔も変わるかもしれない」というようなことが続いた。しかし、現実に変わるのは髪型と気分だけで、それ以外は変わらない。変わると思うのは妄想である……と書いてあったような気がする。理髪店は妄想の時間を提供してくれる。だから、最後にシャンプーで妄想を洗い流す……これが一文の結論だった。理髪店で発想を変えようというような話だったのである。
ぼくはどの本にそんな話が書いてあったのか思い出せないまま、敢えて勇み足をしたことがある。引用文はまったく正しくないだろうが、紹介しようとしたプロットがでたらめではないという確信があった。ところで、先日本棚を整理し、以前に読んだ本をペラペラとめくっていたら、薄っぺらな文庫本に付箋紙が貼ってあった。ロジェ=ポル・ドロワ著『暮らしの哲学――気楽にできる101の方法』がそれ。なんと付箋紙を貼ったページに上記の話を見つけたのである。ぴったり当たらずとも遠からず。ただ、原文は理髪店ではなく美容院だった。先に洗髪することが多い美容院ではこの話は成り立たないと考えて、ぼくは無意識のうちに理髪店に話をアレンジしていたという次第である。