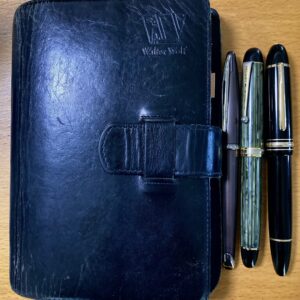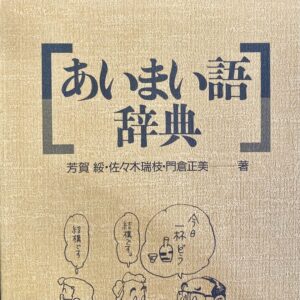冬の風物詩を思い起こそうとしたら、枚挙にいとまがなくて困り果てる。冬の二十四節気は立冬に始まり、小雪、大雪、冬至、小寒を経て大寒に至る。この時期特有の現象や歳時や文化や味覚は尽きない。しかし、冬を年末年始に限定すれば絞りやすい。慣習的に12月29日から1月3日の時期が年末年始とされるので、それに従えばお歳暮、クリスマス、七草粥、成人式は年末年始の風物詩から外れる。
6日間に絞ってもまだ候補はいくらでもある。そこで、世間一般の風物詩の中から自分が見たり経験したりしてきた、いわゆる「マイ風物詩」に絞ることにした。そうすると、縁のない雪、雪合戦、かまくら、つららが消え、あまり興味のない箱根駅伝が消え、故郷がないので帰省が消え、買ったのが一度だけの福袋が消えた。子ども時代には風物詩だったが今はそ、火鉢、みかんが落選。逆に、子ども時代にはなかったイルミネーションや貼るカイロや忘年会は候補から漏れた。
以上のようにフィルターをかけた結果、年末年始の「マイ風物詩ベスト10」はおおむね月並なリストになった。無理もない。風物詩は一人の人生の始まりから終わりまで続いて記憶に残って思い起こされるものだから、極端にリベラルなものは除外されるのである。
餅つき 餅つきとの付き合いは長い。昔は、もち米を持参して餅をついてもらう「賃餅」(関西では「ちんつき屋」)だった。やがて親たちは杵と臼を米屋で借り、もち米を持ち寄って町内でついていた。その習慣がなくなってからは父が電動餅つき機を購入して餅づくりに励んでいた。わが家にも最新鋭のが一台ある。
年賀状 小学生の頃から続けてきた年賀状。創業してからも36年間続けてきたが、昨年を最後にピリオドを打った。メールやSNSのやりとりができるようになった今、年賀状の存在が薄まったのもやむをえない。これを機に、普段の手紙と葉書の出番を増やしたいと思う。
干し柿 柿は秋の風物詩かもしれないが、季節が冬になれば干し柿である。旬の時はそのまま食べるが、寒くなると干し柿をいただく。干し柿は甘いが、これを冬の風物詩として選んだのは、我ながら渋いと自負している。
大掃除 毎年百円ショップで新しい掃除具やシートの類を買ってくる。大掃除を真剣勝負と考えている。特に窓と網戸とベランダは入念にキレイにする。大掃除や整理整頓をするたびに、自分の気分もついでにリセットしているのだと感じる。
大晦日 正月よりも大晦日のほうがワクワクする。除夜の鐘、午前零時までのカウントダウン、おせちのフライングつまみ……。時の流れの中で、この日ほど節目を強く感じる日は他にない。昨年の大晦日は初めてジルベスターコンサートに出掛けた。ワクワクした。
正月/初詣 いろいろな風物詩が正月に集中する。おみくじは数年前に引くのをやめた。今では、元旦のいの一番は雑煮ではなく、初詣である。散歩にちょうどよい距離に真言宗の寺院がある。護摩祈祷の儀に一礼をして、長居はしない。「こちらお接待です」と、日本酒1本を持ち帰らせてくれる。それが初春のお神酒になる。
雑煮/おせち 初詣から帰宅すると、寺院の御神酒をいただき雑煮とおせちを食べる。餅はマシーンによる自家製。おせちは自前のものもあるが、プロ仕様のおせちを知り合いが差し入れてくれる。なお、祝箸は小さなアイテムだが、冬の風物詩には欠かせない。

お年玉 もらうのが楽しみだったお年玉が、子どもや孫らにあげる楽しみに変わってくる。核家族化が著しいので、親族らと直接会う機会が激減した。会って渡せないので、何度か書留でお年玉を送ったことがある。早晩、お年玉は振込になるかもしれない。
書き初め 別名「初硯」。文字通り硯を取り出して、数十年間断続的に書いている。今年の1月2日は出掛けていたので失念した。例年は年末に文字を考えるのだが、それも失念していた。遅くなっても書けばいいが、まだいい文案が浮かばない。
鍋料理 おせちが終わると、ラーメンやカレーやハンバーガーを食べたくなる若者たち。ぼくはと言えば、鍋料理を好む。親と暮らしていた頃の正月の三日目あたりに母が鶏の水炊きを作っていた。そのせいか、牡蠣や鮟鱇の鍋、鰤しゃぶなどの冬の食材を使った鍋料理は今も定番になっている。
総じて言えば、冬の風物詩の主役は正月がらみになる。但し、正月がらみなのに、羽子板、凧揚げ、コマ回し、門松、しめ縄、鏡餅の存在はかなり薄くなってしまった。マイ風物詩を編んでいるうちに、年末年始の自分史が綴られていくのに気づく。



 ‽
‽