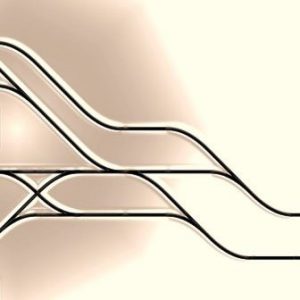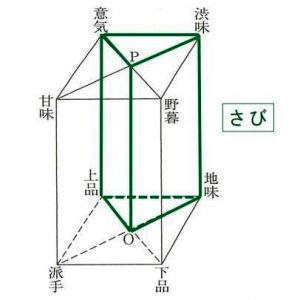現状を分析して問題の原因を探り、しかるのちに問題の解決案を編み出す。これが一般的な企画手順である。ところが、こうして立案される企画は現状に軸足を置いたマイナー改善策の域を出ない。めったなことでは斬新なアイデアが生まれそうにない。
この手順に従うと、できるかぎり情報量を増やそうと躍起になりかねない。情報量に比例して企画の質が上がるという、まったく信憑性のない通念にしがみつく。実際のところ、現状を緻密に分析しなくても、どうすればいいか、どうしたいのかと想いを強くしていれば、アイデアの芽生えに近いところで発想できることがよくあるのだ。
にもかかわらず、人は情報収集に励む。人の情報入力にはキャパがあり、情報源への目配りにも限界がある。日常生活で触れる話題、雑談、テレビのニュース、新聞、雑誌、本だけでかなりの情報量になる。ここにインターネット――画像に動画にSNSにメールなど――が加わる。
21世紀に入って20年足らず。しかし、今日、前世紀に日々接した総量の何乗にも達するほどの情報に晒されている。晒されているだけならまだしも、キャパシティの程をわきまえずに情報を探し求めて取り込もうとする、いや、取り込まねばならないと急かされる。手に入れた情報のほとんどが、あってもなくてもどうでもいいものばかりである。
実際にショッピングに出掛けて知りえる事柄よりも、ネットショッピングにともなう情報のほうが圧倒的に量が多い。店舗ではスペースの限界が購買の選択肢の限界であるが、ネット上では選択肢は無限大。しかし、選択肢の多様性や豊かさが必ずしも賢明な判断を促すわけではない。
仮にかなりの情報量をインプットできたとしても、活用はままならず、情報の在庫ばかりが増え、やがて旬が過ぎて価値を失う。実は、増えていると思うのは幻想で、情報はまたたく間に揮発する。それなら、最初からキャパに見合った情報、何がしかの縁を感じる情報だけにしておけばいいではないか。ともあれ、情報量がアイデアを促すのではない。情報と思考の組み合わせこそがアイデアの源泉なのである。