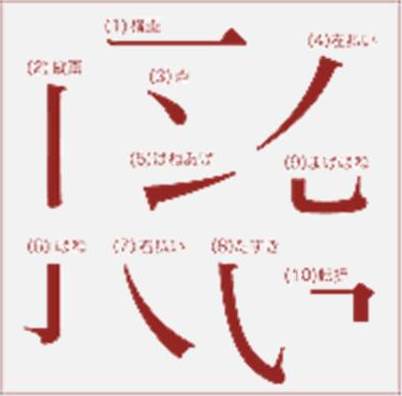企画を読み下せば「画を企む」になる。画とは構想の図であり、大まかなイメージと言ってもよい。樹木そのものであって、枝葉ではない。そのようなアイデアをことばとして編み出し、ことばで紡ぐのが企画案ということになる。
ところで、企画案の大半が現状分析に費やされ事実の羅列に終始することがよくある。そうなると、もはや企画と呼ぶにふさわしくなく、むしろ作業は調査に限りなく近づく。精度を重んじる調査のような企画は型通りの文章で綴られるのが常だから、きわめて事務的になり、面白味や創意工夫に欠ける。
生活実感のある生身の人間として個性と創意を発揮してこそ企画に味が出る。毎年何十何百という企画に目を通すが、そのほとんどが現状分析から導かれた事実を踏まえている。しかし、妥当かつ論理的に現状の問題を分析したまではいいが、出来上がった企画案は二番煎じであり、見覚えのある陳腐なアイデアの寄せ集めになっている。
現状を見るなと言うつもりはない。現状を観察しすぎるとアイデアが発展しづらくなるから注意を促しているのだ。現状分析はじめにありきの企画は、たいてい現状に産毛が生えた程度に終わる。要するに、構想不足のまま進めた企画には展望がないのである。どんな企画でも、企画者個人の願望が出発点になる。小さいかもしれないその願望を叶えようとする情熱から構想が生まれる。
現状分析から出発して立案したものの、やっぱりつまらない、ありきたりだと企画者自身が感じる。これまでの時間を無駄にしないために後付けで表現の衣装を着飾るのが常套手段。内容に応じた表現探しである。このような、思考の翻訳作業をしているかぎり、企画のことばが力を発揮することはない。すべての作業に先立って、まずコンセプトという、ことばの概念を編み出す必要がある。
不確かで形の定まらないコンセプトを、ひとまずことばとして仮押さえする。そこから可能性をまさぐり、ああでもないこうでもないと考える。その過程で事実を参照し不足する情報を仕入れる。必然、ラフなコンセプトのことばは徐々に論理的に強化され、企画のことばとして完成形に近づく。
コンセプトのことばが論理のことばを触発するのであって、その逆ではない。現状分析から入れば論理のことばが優勢になり、後付けのコンセプトのことばが取って付けたように浮き足立つ。企画とはことばに始まってことばで完結する。便宜上、コンセプトのことばと言い、企画のことばと表現してきたが、企画とはことばそのものであると言っても過言ではないのである。