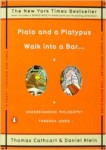最初通読して「なるほど」と感じ入った見解だったが、もう一度読み直してみたら「ちょっと待てよ」と再考したくなることがある。そのつど、一度だけではわからないものだと痛感する。もう一度読んでみて「やっぱりそうなんだろう」と思えば、知の度合はともかく、暫定的に納得しておくしかない。逆に、「おかしい」と感じたことを二度目に読んで「間違いなくおかしい」と思い至ることもある。
ある建築史家の講演での話を引いた新聞記事があった。「日本人がなぜ赤レンガの建物が好きなのか」という理由が二つあるという。一つは縄文時代以来、日本人が延々と土を焼いてきて、焼き物や瓦が生活の原風景にあり、レンガで心が休まるというもの。もう一つは、日本のレンガ建築の多くは英国にルーツを持ち、近代日本人の英国への思いが愛着の背後にあるというもの。この話を読んで、ぼくは最初に「何か変」と直観的に反応し、もう一度読み直しても「変」という思いは変わらなかった。
まず、縄文時代以来土を焼いてきた日本人の生活の原風景にレンガはずっと存在してなどいなかった。もしレンガへの憧憬があったのなら、メソポタミア文明のようにレンガで建造物を作っていたはずである。わが国がレンガ工場を作ってレンガを生産し始めたのは1870年になってからのことだ。次に、仮に縄文時代以来の「レンガDNA」を唱えるのなら、わざわざ近代になってからの英国の影響を引き合いに出すこともない。もし確かに英国の影響を受け、それがDNAと相まってレンガ建築好きを助長したのだとしても、では、日本人はなぜ明治・大正期の数々のレンガ建築を解体して、代わりに無味乾燥な建築物を量産していったのかという説明がつかない。経済成長はDNAを駆逐する?
縄文時代と英国という二つの事象を一つにまとめ、本来相互に関係がないのに、無理にこじつけているかのようだ。これを「牽強付会」と言う。なぜこういう話になってしまうのか。おそらく最近東京駅がレンガ造りに再現されたり、古いレンガの建築物を一部でも保存しようという動きがごく稀に出てきたりするからだろう。個人的には赤レンガが好きである。しかし、赤レンガの家を建てようとは思わない。観賞者として赤レンガを好むことと、それを生活に自ら取り込むこととは別のものである。赤い色をこよなく愛しても赤いスーツを着ることにつながらないように。
土を焼いて器や瓦を作りはしたが、レンガによって住まいを囲おうとしなかった日本人。他方、レンガを積んで住居や周辺の壁を固めた民族がある。この相違点にこそ考察に値する妙味があると思うのだ。この点については、たとえば芦原義信『続・街並みの美学』の次の一節に興味を覚える。
オットー・ボルノーやハイデッガーはその実存主義的立場から、建築における壁の存在の重要性を強調している。そして堅固な人為的な壁によって内部に庇護性のある空間をつくりだし、そこに人間が住むことによってのみ自己の本質の実現に到達する(……)
空間とは、言うまでもなく、「場」である。人が生活する場である。もし人がそこに居合わせないなら、それは場にはなりえない。その場を堅固にレンガの壁で固めることを「生きること、命を守ること」としたヨーロッパの人々がいたのであり、いるのである。英国の話を持ち出すのなら、“An Englishman’s house is his castle.”(英国人の家は彼の城である)こそがレンガの意味を説くのにふさわしい。強くなければ家ではない、というわけだ。赤レンガが好きだからレンガを積んだのではなく、庇護性のある空間のために居住空間を囲ったのである……と考えるほうが素直ではないか。最後になるが、ぼくは居住者ではあるが、建築の素人である、念のため。