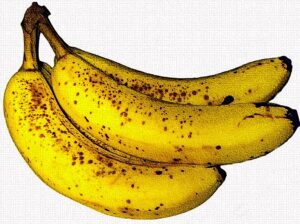二十代の頃の職場に物静かで口数の少ない同僚Iがいた。ある日、上司とぼくが喫茶店に誘ったら付き合ってくれた。上司が当たり前のように「コーヒー3つ」とウェイトレスに告げた瞬間、「あのう、コーヒー飲まないんです」とI。紅茶と思いきや、彼が注文したのはシュガー抜きのホットミルクだった。上司が「らしいねぇ」とつぶやいた。
ホットミルクを注文したのがIらしいのなら、ホットミルクの愛飲家は物静かで口数が少ないということになる。ある辞書は、らしさとは「飾らずに備えている独自性」と定義している。ホットミルクを注文するのは彼らしい、コーヒーを飲まないのも彼らしい、喫茶店に誘ったら断ると思ったが、付き合ってくれたのは彼らしくない……。
上司は彼のことをあまりよく知らないのに、今しがたホットミルクを注文したことを彼らしいと言った。本人の中で自分の独自性とホットミルク嗜好がつながっているはずがない。他人である上司が勝手にらしさを決めて、「ふさわしい」だの「いかにもな感」だのと評しているに過ぎない。
「職人らしい職人」という言い方がある。あれは何を表現しているのか。職人らしいと言えるためには職人が備える条件や資質を知らねばならない。職人がどういう人なのか知らずに「親方は職人らしい職人だなあ」などとつぶやけない。「あいつらしい阿漕なやり方だ」と言えるためには、あいつのことを知り尽くしている必要がある。
ここしばらく寒い日が続いた。気象予報士が「明日も冬らしい冬になりそうです」と言うのを何度も聞いた。「西側に高気圧、東側に低気圧が位置する気圧配置」が冬型の典型ならば、冬らしい冬とはそんな冬型の典型ということになる。しかし、例年の冬や平年並みの冬は一定ではないから、冬らしい冬がどんな冬なのか、気象の素人にはよくわからない。
ナポリ生まれのイタリアの哲学者、ジャンバッティスタ・ヴィ―コ(1668-1744)は「真実なるものと作ったものは換位される」と言った。作ったものでも真実らしければ――たとえ真実という確証はなくても――ほぼ真実だと言えるかもしれない。コーヒーらしいコーヒーはほぼコーヒーなのである。