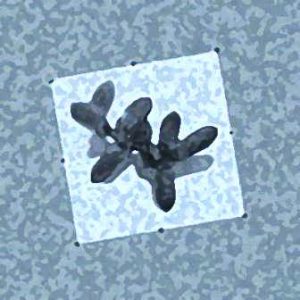その場その瞬間、ある刺激に反応して経験を刻印する。その積み重ねによって新しい環境や状況に活用可能な固有の経験の体系が形成されていく。
経験を刻印する前提に、諸々の他者、事物、状況から成る環境への反応と適応が求められる。安穏と時の過ぎゆくままに生活を送り仕事をするのではなく、一人の個性的な人間の生命に関わるものとして経験を「肉化」しなければならない。これが習慣の形成ということであり、そのつどゼロから考えなくても生き延びる暗黙知になりうる。
人間にとって、〈環世界〉の認識装置は通常視聴覚であり読解である。聞き流すのではなく聴き取る、ぼんやり眺めるのではなく観察する、文字面を追うのではなく踏み込んで意味を解読する。ぼくたちは誰もが同じように言語を読み聴きし、現象を見ているのではない。人それぞれに経験の体系があり、それを辞書や受容器のようにして読み聴き、それに照らし合わせながら文脈や場面を通じて類推的に解釈している。環境の中のなじみの薄い情報も、この経験の体系によって搦め取ろうとする。
日本語だから立ち止まって深く考えないが、外国語の学習を想起すればよい。たとえばフランス語の文章を読む時に知らない単語に出くわす。既に知っている単語、文脈、そして知識によってその単語の意味を類推する。それはフランス語であるが、同時に日本語や英語の過去の学習経験を総動員している。文章の解読とは、全経験を装置とした判読の闘いでもある。裏返せば、経験の内にまったく手掛かりがなければ判読は不可能だということだ。
なにげなく読みなにげなく聞くことと、もう二度と出合わないかもしれないという思いで読み聴くことの違いは学びの真剣さの差にとどまらない。前者は単に行為することであるが、後者は経験することである。経験とは環境に適応しようとする生き様にほかならない。
適応力・判断力・認識力は経験の発動頻度におおむね比例する。誰も白紙状態のまま一人で生きることはできない。たとえごくわずかな知識であっても、たとえ狭い参照枠しか持ち合わせなくても、自らの経験の知によることなしに対象を捉えることはできないのである。
「全生物の上に君臨する客観的環境なぞ存在しない。我々は、認識できたものを積み上げて、それぞれに世界を構築しているだけだ」
(日高敏隆)
この認識を〈イリュージョン〉と呼ぶ。認識量が乏しければイリュージョンすらも枯渇し強く歪んでしまうだろう。どんなに多彩な経験を積んでも認識に到らねば、経験は生かされない。そして、経験が認識できたとしても、小窓から世界を覗き見しているようなものであり、もしかすると幻想に近いものかもしれないと覚悟しておく必要がある。