二十代の終わりに転職して数年間、その後創業してからも十年間、合わせると二十年近く国際広報に従事したことになる。日本企業の海外向けPRであり、具体的には英文の執筆・編集の仕事をしていた。英語圏出身の専門家との協同作業だが、英文スタイルや細かなルールについては意見がぶつかることが多かった。カンマを打つか打たないか、セミコロンでつなぐのか、この箇所の強調にはイタリック書体を使うのか、一文を二文にするのか……など、最終段階では単なる文字校正以上の調整作業に疲れ果てたものだ。
英語は日本語に比べて、一般的に文型が変化しにくい。中学生の頃に習った、例の五文型を思い起こせばわかる。S+V、S+V+C、S+V+O、S+V+O+O、S+V+O+Cの五つがそれである。S=主語、V=動詞、O=目的語、C=補語の四要素のすべてまたはいずれかを組み合わせるわけだが、どんな文型になろうと、主語と動詞がこの順で配列される。目的語と補語も動詞の特性に従属する。動詞が文型の構造を決定するのである。文型が五つしかないのだから、英語は数理的な構造を持つ言語と言ってもいい(と、拙著『英語は独習』でも書いた)。
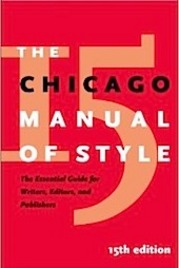 例文紹介を割愛して話を進める。単文の文型なら文章は動詞によってほぼ支配されるから、極端なことを言うと、簡潔に書けば誰が書いても同じ文章になる。にもかかわらず、編集者やライターはなぜ通称『シカゴマニュアル』(The Chikago Manual of Style)という、900ページもの分厚い本を手元に置いて参照するのか。よくもここまで詳述するものだと呆れるほど細目にわたって文体や表記のありようを推奨しているのである。察しの通り、文章は単文だけで書けない。必然複文や重文も入り混じってくる。さらに、記事になれば一文だけ書いて済むことはない。段落や章立てまで考えねばならない。こうして、文体や表記の一貫性を保つために気に留めねばならないことがどんどん膨らんでいくのである。
例文紹介を割愛して話を進める。単文の文型なら文章は動詞によってほぼ支配されるから、極端なことを言うと、簡潔に書けば誰が書いても同じ文章になる。にもかかわらず、編集者やライターはなぜ通称『シカゴマニュアル』(The Chikago Manual of Style)という、900ページもの分厚い本を手元に置いて参照するのか。よくもここまで詳述するものだと呆れるほど細目にわたって文体や表記のありようを推奨しているのである。察しの通り、文章は単文だけで書けない。必然複文や重文も入り混じってくる。さらに、記事になれば一文だけ書いて済むことはない。段落や章立てまで考えねばならない。こうして、文体や表記の一貫性を保つために気に留めねばならないことがどんどん膨らんでいくのである。
文体や表現にもっと融通性があるはずの日本文のルールブックは、シカゴマニュアルに比べればずいぶん貧弱と言わざるをえない。一見シンプルな構造の英文に、それを著し編む上で極力準拠すべきルールがこれほど多いことに衝撃を覚えた。ぼくは話し聴くことに関してバイリンガルからはほど遠い。つまり、日本語のほうが楽であり英語のほうが苦労が多い。しかし、こと英文を書くことに関してはさほど苦労しなかった。それでも、スタイル面での推敲にはかなり時間を費やさねばならなかったし、同僚のネイティブらとああでもないこうでもないと話し合わねばならなかった。アルファベット26文字で五文型しかない言語なのに……。いや、そうであるがゆえに重箱の隅をつつく必要があるのかもしれない。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットが混在し、縦書きでも横書きでも紙誌面の構成ができてしまう日本文。そこに一貫性のあるルールを徹底的に適用しようと思ったら、すべての文章にひな型を用意しなければならなくなるだろう。際限などあるはずもない。ワープロの出現によって書けない漢字を変換する便利さを手に入れたが、はたしてその漢字を読者が読み判じることができるかにまで気配りせねばならない。マニュアルに基づいてそんなことをしていたら文章など書けなくなってしまうだろう。
日本語にあって英語にないものを列挙すればいくらでもある。それほど二つの言語は異なっている。とりわけ漢字とふりがなの存在が両者の間に太い一線を画する。たとえば“hippopotamus”と英語で書いて、それが読めなくても発音記号を付けることはない。日本語では「河馬」と書いて「かば」とふりがなを付けることができる。いや、本文で「かば」と表記してもいい。このとき「カバ」という選択肢もある。しかも、河馬と書いて「バカ」というルビを振る芸当までできてしまう。そう、まさにこの点こそがスタイルブックにいちいち準拠するわけにはいかず、書き手の裁量に委ねられる理由なのだ。
「顰蹙を買う」とするか「ひんしゅくを買う」とするか、ちょっと斜に構えて「ヒンシュクを買う」とするか……。顰蹙などと自分が書けもしない漢字をワープロ変換ソフトに任せて知らん顔してもいいのか。時々神妙になってキーを叩けない状態に陥る。英語では知らない単語は打ち込めない。そして、自力で打ち込めるのなら、おそらく意味はわかっているはずである。ワープロ時代になって困ったことは、書き手自身が書けもせず意味も知らない表現や漢字を文章中に適当に放り込めるようになったことだ。手書きできる熟語しか使ってはいけないという制限を受けたら、現代日本人の文章はかなり幼稚に見えてくるだろう。
ところで、顰蹙は何度覚えてもすぐに忘れる。ひらがなで書くか別の用語を使うのが無難かもしれない。他に、改竄も「改ざん」でやむをえず、放擲も時間が経つと再生不可能になる。憂鬱などはとうの昔に諦めていて、「ふさぎこむ」とか「憂う」とか「うっとうしい」などと名詞以外の品詞で表現するようにしている。
