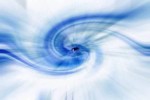渦
彼は古書店でフランス語の短編小説集を手にした。そして、本をめくっているうちに偶然この一編を見つけた。自ら体験した現実が小説になっているのを知って彼は驚愕し打ち震え、その震えはしばらく止まらなかった。著者は彼には聞き覚えのない名前だった。
『トゥールビヨン公園』と題された原作。題材となったエピソードはトゥールビヨンの街の人々にはよく知られていた。しかし、二人称で展開されるこの小説が書かれてからは誰も実話だと思わなくなった。やがて市民たちは、これは実話ではなく作り話なのだと自らに言い聞かせるようになったという。
トゥールビヨンの街には楕円形をした公園がある。樹林が繁り花壇がよく手入れされ、ベンチも十分に据え付けられている。週末や日曜日には、小市民的生活に充足している人々がやってくる。誰もが幸せそうに見える。そう、きっと幸せに違いない。確信はないけれど、たぶん幸せだろう。でも、時々つらいことや嫌なこともあるはず。いや、もしかすると幸せそうな顔をした不幸な人がいるのかもしれない。
ところで、きみは仕事を嫌悪し始めていた。小手先の作業はさほどでもなかったが、大きな負荷がかかる職務には耐えがたくなっていた。単調で平凡な仕事で十分だった。そのように雇い主に申し出ればよかったが、心の中で訴えるばかりで、口には出さなかった。仕事が嫌になり始めると、私生活がおもしろくなくなってきた。きみに家庭があったわけではない。私生活とは個人生活にほかならなかった。ともあれ、白紙であることが許されない、色塗られた時間の刻一刻が大きな負担になってきた。
こうして、きみはもはやこれまでのきみではなくなった。知人や友人と会うのが嫌になった。読書が嫌になった。大好きなカフェに行くのも嫌になった。話すのが嫌になったし、あくびをすることすら嫌になった。指を動かすことも、まばたきすることも嫌になった。
そして、いま、ついに生きることもなんだか嫌なことだと思い始めている。
しかし、いろんなことが嫌になったからといって、生きることだけは嫌になってはいけないだろう……むろん生活の中の小さな不快すら許せないけれど、嫌な気分を自覚できているのは生きている証だし、何から何まで懐疑しても、その懐疑している自分だけは疑いようがない……なんて、まるでルネ・デカルトのようだ……でも、我思うゆえに我ありという具合にはいかない……。独りであれこれ悩んでもはじまらない、こんな時はたぶん誰かに意見を求めるべきなのだろう……こんなふうにきみは考えている。
それでも、顔見知りに相談する気は起こらない。きみは、知り合いが本音で語ってくれるとまったく思わない。むしろ、見知らぬ人たちのほうがよほどいいはずだと思い、相談を持ちかける場所をトゥールビヨン公園にしようと決めるのである。
きみはトゥールビヨン公園の入口にやって来る。大勢の人たちが目に入ってくる。子ども連れの夫婦、ボール遊びに興じる少年たち、鳩にパンくずを与えている老人、巡回中の警察官、静かな樹林の方へ歩いていく若い男女、早足で歩く学生、ベンチに座って散歩人を眺める遊び人……。きみは無作為に相談相手を選ぶことにする。
大きめのベレー帽を深めにかぶった中年男がいる。ベンチの端に腰掛けて雑誌を読んでいる。
「こんにちは。いきなりで恐縮ですが、なぜ生きなければならないんでしょう?」ときみは尋ねる。
男は面倒臭そうに雑誌から目を離し、帽子を髪の生え際のほうへと突き上げた。
「それは、あなたね、雑誌を読むためだよ。死んでしまったら、このトゥールビヨン公園で雑誌を読めないからね」
男はあっさりとそう言ってのける。
「ありがとうございます。とても……」
きみが礼を言い終えないうちに男は雑誌に目を戻し、くすぐられたような笑いにのめり込んでいく。鳩が二羽、きみの足元に近づく。きみは無視する。
次にきみはバラの花壇づたいに樹林の中へ入ろうとしている若い男女の後を小走りに追う。
「こんにちは。失礼ですが、なぜ生き続けなければならないんでしょうか?」
とっさの質問に女が身構えて素早く男の背中へ逃げる。男は険しい目つきできみをきっと睨みつけ、威嚇するように胸を張る。
「恋のためだよ、恋の。恋のために生き続けるのさ。あんたにはわからないだろうけど……」
女が舌なめずりして喉で笑い、男は手首を振って、きみにどこかへ去れと合図をする。
「どうも……」
きみが軽く下げた頭を元に戻すと、二人はこれ見よがしに腕を組み直して樹林の奥へと消えていく。梢を微かに揺するそよ風がきみにも吹いてくる。だが、きみの感覚は反応しない。
しばらく歩いていくと、仔犬を連れた婦人に出くわす。飼犬だけを見るためにかけている眼鏡の輪郭で、その女が他人に無関心であることがわかる。しかし、質問をしてまずいわけはないだろうときみは思う。
「こんにちは。散歩中のところお邪魔して恐れ入ります。なぜ生きることはたいせつなんでしょうか?」
女はきみを無視し、鎖を引っ張る飼犬の尻尾に目をやる。なおもきみは同じ質問を繰り返す。女は絶望的なため息をつき、ヒステリックに語気を荒げる。
「できるかぎり人間から離れて、犬と暮らすためにたいせつなのさ。あんたみたいな野暮な男を憎むためにも生きなきゃならないんだよ。わかったかい!?」
そう言うなり、女は声のトーンを淫らに落として続ける。
「それとは関係ないけどさ、あんたね……くだらない男に抱かれるよりは、ふふ、犬を抱くほうがよほど快楽的なんだよ」
女が喋っているあいだに仔犬は花壇に入り込もうとしている。仔犬の後を追いながら女は叫ぶ。
「ひとりで逃げないでおくれ、あたしも一緒だよ!」
仔犬が甲高く鳴く。しかし、きみにはその鳴き声はほとんど聞こえていない。
こうしてきみはトゥールビヨン公園で休日を過ごす人たちに次から次へと同じ質問を繰り返していく。そのつど反応は様々だが、誰もがなぜ生きるのかについて明快に語る。きみは不思議な気分になっている。これといったたいした理由もないくせに、なぜ精一杯生きるのかを誰もが追求しているんだ……きみはそう思い、ほんの少しだが、励まされたような気がし始めている。
トゥールビヨン公園の光景を振り返り、緑と人々を覆っている透き通った青い空を確かめ、さほど強くない陽光に後押しされるようにして、きみは出口付近へ戻ってくる。小さな雲がやけに目立つ。
そこにはきみと年格好の似た、表情の暗い男性が立っている。だだっ広いトゥールビヨン公園を見渡しているが、焦点の落ち着き場所が見つからないらしい。男性の視線がちょうどきみのいる場所で止まる。虚ろな目がきみに焦点を合わせると、男性はゆっくりと歩み寄ってくる。そして、おどおどした声を絞り出してきみに話しかける。
「お急ぎのご様子ですが、いいでしょうか。一つ質問があるのです。なぜ生きなければいけないんでしょうか?」
不意をつく問いにきみは一瞬困惑する。だが、もうすっかり言い慣れた問いなので、すぐに冷静さを取り戻す。しかし、いざ答えようとしても、言葉が口をついて出てこない。言い慣れはしているが、聞くのは初めてで、しかもその問いには一度も答えたことがないからである。
長く考えては相手が気の毒だと思い、きみはさほど深く考えず、しかし少しよどみながら告げる。
「なぜ生きる……その必要性……と言うことでしょうか……。そうですねぇ……特に……ないのかもしれない……」
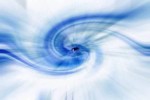
軽いつぶやきのつもりだったが、男性には衝撃を与えたらしかった。なぜなら、消え入りそうな声で「やっぱり、そうでしたか」と言うなり、男性は突然きみの目の前で、小さな、けれども、力のある渦に変化したからである。その渦はどうやら男性のこらえ続けてきた溜息のようであった。きみはあまりの急激な変化に驚き、反射的に地面に伏せなければならなかった。それほどその渦は激しく巻き上げ始めていた。
渦はますます大きく膨らみ、たちまちのうちにトゥールビヨン公園の出口付近から楕円形の中心方向へと広がり吹き荒れた。ぐるぐると回転しながら、そこに居合わせている人たちの溜息を吸収し、決して衰えることなく地面を烈しく撫で続けた。
だが、見た目ほど渦は破壊的ではなかった。きみはその渦の中でしばらく身を伏せていた。きみの皮膚感覚は、そこが静寂で平和な世界であることを冷静にわきまえていた。鳩がせわしなく地面をつつき、渦の風で梢がざわめき、そして犬が相変わらず甲高く鳴いていた。
岡野勝志 作 〈1970年代の短編習作帖より〉
 犬と猫の夜語り
犬と猫の夜語り