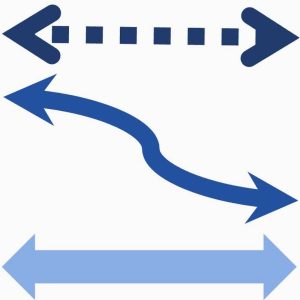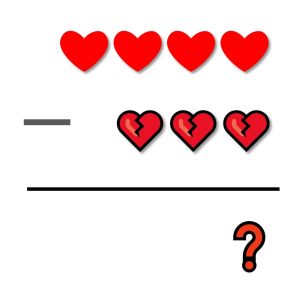あることばの意味を調べようとして辞書を引く。そのことばの見出しの下に語義が書かれている。読めばわかったような気になるが、実はことばは単独で意味を持っているわけではない。ことばは別のことばと対比されてはじめて意味を持つ。仮に二つのことばをAとBとするなら、〈A⇔B〉という対義や対立の関係にしてみると意味が鮮明になってくる。
「長い」「多い」「高い」「表」「右」「開く」などは単独では何のことかわからない。「そんなことはない。わかってる」と反論されそうだが、「長い⇔短い」「多い⇔少ない」「高い⇔低い」「表⇔裏」「右⇔左」「開く⇔閉じる」などと、〈A⇔B〉として対義させてきたから徐々に意味が明快になったのである。
AとBは同時に成立しない。つまり、「AでなければBであり、BでなければAである」という対義語の関係にある。よく似た関係が〈二項対立〉だ。上記の長短、多少、高低、表裏、左右、開閉のような正反対の関係ではない。たとえば教師と生徒は同時に成立することもあるし、「教師でなければ生徒、生徒でなければ教師」ともかぎらない。こういう関係が二項対立。但し、対義語と二項対立のどちらにも顔を出すAとBもある。
誰が見ても二項が矛盾または対立している普遍的な二項対立もあれば、価値観によって敢えて二分化する特殊な二項対立もある。白の対義語は黒だが、赤も対義語だ。では、赤の対義語は白かと言えば、たしかにそうだが、黒もありうる。つまり、白と黒と赤は三つ巴の関係でもある。白⇔黒、黒⇔赤、赤⇔白の背後には固有の価値観が見え隠れする。
以前、人間の資質や性向を自分なりに二項対立の関係でとらえたことがある。定番的なものもあれば、強引な創作だが二項を見る視点を変えてくれたのもある。ここにリストアップしておく。
臆病 ⇔ 勇気
不安 ⇔ 自信
他力 ⇔ 自力
甘え ⇔ 責任
反応的 ⇔ 主体的
寡黙 ⇔ 多弁
儀礼的 ⇔ 親密的
見栄 ⇔ 潔さ
待つ ⇔ 動く
我 ⇔ 無我
怠惰 ⇔ 勤勉
遅疑 ⇔ 拙速
思いつき ⇔ 熟慮
一つの答え ⇔ 複数の問い
こだわり ⇔ 柔軟性
聞き流し ⇔ 傾聴
先送り ⇔ 即実行
鈍感 ⇔ 気づき
遠慮 ⇔ 踏み込み
タテマエ ⇔ ホンネ
分裂 ⇔ 統合
慌てる ⇔ 落ち着く
迷い ⇔ 決断
ポーズ ⇔ 自然体
情報依存 ⇔ 思考主導
蒙昧 ⇔ 教養
対立 ⇔ 対話
承認願望 ⇔ 批判受容
人の振り見る ⇔ 我が振り直す
自分世界 ⇔ 生活世界
一人称 ⇔ 二人称