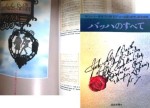鮮やかに直線を引く飛行機雲を目にした。飛ぶ機体も、背景に青をいただく白という図も何度も見上げてきた。しかし、いつも同じようには見えない。季節の空気で気配は変わるし、しばらく続く残影も気分によって変わる。すべての飛ぶ飛行機は「着陸」を目指す。つまり、ある地点に到着する。高空にある飛行機を見るたびに「どこへ行くのだろう?」と素朴に思う。けれども、すでに離陸したからこそ着陸がある。「どこから来てどこに向かうのだろう?」と想像すれば、出発と到着が一つにつながる。
若かりし頃に読んだアルチュール・ランボーの一篇を連休中にふと思い出した。もちろん、半世紀近く前の詩を丸暗記しているはずもない。だが、偶然とは不思議なもので、この飛行機雲を見上げる直前に、古本屋で懐かしいランボー詩集に巡り合い手に入れていたのである。買ってはいたが、数冊のうちのついでの一冊であり、ページすらめくっていなかった。飛行機雲を見たその場では「離着陸」を連想し、もう一度写真を見てランボーの“イリュミナシオン”の中の『出発』がよみがえり、そして詩集を買ったことを思い出したのである。早速その一篇を探した。フランス語と日本語の併記で紹介されている。
DÉPART
Assez vu. La vision s’est rencontrée a tous les airs.
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie. ―― O Rumeurs et Visions!
Départ dans l’affection et le bruit neufs!
出発
いやほど見た。幻はどんな空気にも見つかった。
いやほど手に入れた。夜ごと、町々のざわめき、陽が照っても、いつもかもだ。
いやほど知った。かずかずの生の停滞。 ――おお、ざわめきと幻よ!
新たなる愛情と響きへの出発!
フランス語は話すのは苦手、聴くことはさらに苦手である。苦手なのはほとんど口と耳を使って学習してこなかったからだ。それでも、辞書があれば、英語とイタリア語からの連想も交えて、ある程度は読み取れる。まったく偉そうなことは言えないが、この詩のフランス語はさほど難しくない。しかし、この訳で原詩のニュアンスが伝わっているのだろうか。上田敏ならどんなふうにこなれた日本語で紡いだだろうかと想像した。好奇心から他にどんな訳があるのか調べてみた。『ランボオ』について書いている小林秀雄の訳を見つけた。
見飽きた。夢は、どんな風にでも在る。
持ち飽きた。明けて暮れても、いつみても、街々の喧噪だ。
知り飽きた。差押えをくらった命。――ああ、『たわ言』と『まぼろし』の群れ。
出発だ。新しい情と響きとへ。
これはどうなんだろう。先の訳よりも切れ味があるような気はする。しかし、こうして二つの訳を比較してみると、同一の原詩を訳したとはとても思えないほど感じるものがかけ離れてしまう。もう一つ別の訳がある。
見あきた あるだけのものは もはや見つくした
聞きあきた 夜となく昼となく いつもお定まりの町々の騒がしさ
知りあきた 生命もたびたび差し押さえられた ――ああ やかましい雑音と仇な幻
出発だ 新たな情緒と新しい雑音のうちに
どの訳に最初に出合うかによって詩人に抱く印象が変わる。そして、もし最初に読む訳詩だけしか知らずにいたとしたら、決定的である。詩には小説の翻訳以上に訳者の思いが反映される。詩人と訳者の合作を読んでいるようなものだ。
ランボーの署名が残っている。その直筆に幼さを感じる。それはそうだろう、37歳で生涯を終えたランボーが詩作したのは15、6歳からのわずか数年間だけだったのだから。誰もが認める早熟の天才。そのサインの筆跡が示す通りの幼さを見せながらも、ランボーは奇跡的に現れて、「不思議な人間厭嫌の光を放ってフランス文学の大空を掠めた(……)」(小林秀雄)、そして、不気味な空気を詩編に残して、彼は消えた……。
早逝の詩人ゆえ当然寡作である。全詩を読み尽くすのに、念には念を入れて仏和で味読したとしても、一日あれば十分である。ぼくらの世代のちょっとした文学青年なら十代か二十代前半に読んでいる。とうの昔のことだからすでに本を処分しているかもしれない。ぼくもそんな一人だ。半世紀近くを経て偶然手元にあり、今ページが繰られる。そう、あの飛行機雲から『出発』を思い出した偶然の成せる業である。ところで、最近の若い人たちはランボーを読むのだろうか。