ゼノンの論証のパラドックス。現実にありそうもないことを、さもありうるかのように論証する試みである。走ることが遅い者は、速い者よりも前を走っているかぎり、追いつかれず抜かれることはない……なぜなら足の速い者が遅い者がいた時点に着く時には、遅い者はすでにそこから先に行っているからである……というパラドックスがその一つ。
そんなもの一気に追い越せるではないかという反論をしても、ゼノンは言う、「足の速い者が追い越すためには、足の遅い者がすでに通過した地点にまず達しなければならない……しかし、その地点がどこであろうと、足の速い者が着いた時点で、足の遅い者は必ず少しでも先に行っているはずだ」と。
上記のパラドックス物語を競演するのが「アキレスと亀」である。どんなに足の速いアキレスでも、いったんのろまな亀にハンデを与えたら最後、永久に追いつけない。先月関東に出張した折り、そんなゼノンのパラドックスを想起させる文言に出合った。東京駅の山手線ホーム、電光掲示板の電車案内文がそれである。
終点まで快速に抜かれません。
この普通電車は快速に抜かれない、それはちょうど亀がアキレスに抜かれないのと同じである……。まさか。
これは書かれた日本語である。決して声に出してみる日本語ではない。こういう文章を見ると、こう書かざるをえない事情があったのかと穿った見方をしてしまう。「終点にはこの電車が先着します」と肯定文で書かないのは、快速以外に別の何かが先着するからだろうか。あるいは、この電車と快速のどちらが早く終点に着くでしょうかというクイズに対する正解発表なのか。つまり、この電車は快速に抜かれないので、終点に着くのはこの電車です、というつもりか。
「次に6番線にまいります電車は……」とか「次の列車は……」に慣れているぼくには、「今度6番線にまいります電車は……」や「今度の列車は……」に違和感を覚える。それでも、何度か聞いていればなじめそうなので、「次」か「今度」かどっちがいいかなどとも考えないし、「今度」の揚げ足を取ってやろうなどとも思わない。慣れの問題であるから。
「快速に抜かれません」には生涯慣れることはないだろう。「この電車は○○駅で快速通過待ちをします」と聞いていつも悔しがる乗客への励ましのつもりなのに違いない。「お客さん、いつもいつも後から出る快速を先に行かせてごめんなさい。でも、この電車はね、快速に抜かれませんよ。誇らしく優越感を抱いて終点までどうぞ」というつぶやきに見えてきた。



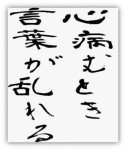


-150x108.jpg)


