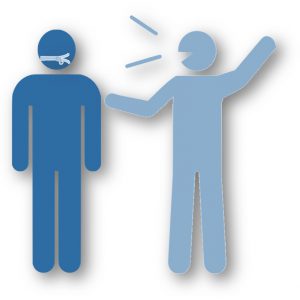「紙一重の差」などと言うが、対戦して仮に10連敗したら、僅差ではなく大差なのではないか。いや、一つの対戦に限れば紙一重の差で、それが10回続いただけと苦しい弁。いったい紙一重とはどのくらいの差なのか……誰も知らない。
🔄
先日、ビストロで食事をした。食後にコーヒーの香りのする熱い白湯が出た。いかに料理がよくても、最後の一杯のコーヒーがお粗末ならリピートしない。店を出てコンビニの100円コーヒーで口直しをされたら屈辱的である。
🔄
九種二貫ずつの刺身の盛り合わせ、850円。「うまい!」の前に「安い!」と迂闊にもつぶやいてしまった。〆に注文したうちわエビの味噌汁が200円。また「安い!」と言いかけて思いとどまる。自ら料理の値打ちを下げてはいけない。「真心のこもりし味覚秋近し」と詠んでお勘定してもらった。
🔄
焙煎のアロマを微風が運ぶ。この季節、窓を少し開けておけばカフェに看板はいらない。
焙煎のアロマを微風に乗せてぼくを誘ったはずなのに、カフェのプレートはまだ“closed”。
🔄
自分が使う喋りの技と同じ技でころりと丸め込まれてしまうのが人の常。
🔄
縁があるか縁がないか。あるギョーカイでは「あの人を知っている」と「あの人を知らない」の差は決定的である。だからこそ自ら縁を求める者が後を絶たない。しかし、縁は成り行きに任せるのがいい。縁があればありがたく思い、縁がなければ「縁がなかった」と思えばすむ。縁とはそういう類のものだ。
🔄
ほとんどの民族は文字を発明した。記憶に自信がなかったから。
同じ理由から、人類は付箋紙を発明した。できることなら脳に直接貼り付けたいのだけれど、さすがに無理なので、やむをえず本やノートに貼っている。付箋紙ごときで格段に仕事がはかどったり記憶がよくなったりするはずはないが、付箋紙を貼ろうと意気込めば、見過ごしがちだったものが稀に見えることがある。