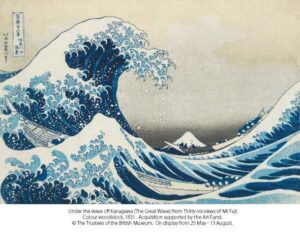📝 先日、第42代米大統領の名前がとっさに出てこなかった。十数秒後に「ヒラリー」が浮かび、すぐにビル・クリントンにつながった。以前覚えて知っているはずのことをとっさに思い出せなくなるのを「ど忘れ」という。では、とっさに思い出すことをどう呼べばしっくりくるか?
📝 食レポだったと思うが、ある人が「この料理は情報が多い」とつぶやいた。情報が多いという表現は平凡だが、料理と結びついて新鮮に聞こえた。食材、盛りつけ、調理方法、ことばにしづらい味……コメントしたいことがいくらでもあるという感じか。そう言えば、自宅にいても仕事をしていても、ものすごく情報の多い日とほとんど情報のない日がある。情報の多い日は疲れるが、情報の少ない日は物足りない。
📝 中原中也「帰郷」のラスト2行。
あゝ おまへはなにをして来たのだと……
吹き来る風が私に云ふ
この冬一番冷えた1月24日、強い寒風に凍えそうになって半コートの襟を立てた。「あゝ おまへはカイロを貼ってくるべきだった」と、吹き来る風が云った。
📝 ノーベル賞受賞者のスイスのディディエ・ケロー博士。太陽系外惑星の最初の発見者だ。地球外や太陽系外惑星に生命体が存在する可能性は? という問いに博士は答える。
「宇宙のどこかに生命が存在する、と私は確信している。理由は簡単で、恒星の数も惑星の数も限りなく多いから。逆に、地球上にしか生命がいないと考えるほうが不自然だ」
なるほど。しかし、「宇宙には地球以外に生命が存在しない」とぼくは確信している。理由は簡単で、一度もお目にかかったことがないから。逆に、宇宙のどこにでもいると考えるほうが不自然だ。この宇宙の中で地球にしか生命体がいないという奇跡にそろそろ人類は気づくべきではないか。
📝 のべつまくなしに癒されたがる人、結構回りにいる。もう十分に癒されているように見えるし、これ以上何をどれだけ癒されたいと言うのか。「癒されたい」とか「ああ、癒される~」とかを耳にすると、ちょっとキモチ悪い。癒しは、質ではなく、量的に求められるようになった。残念である。ほどよく疲れるほうがよほど上等な癒しだと思う。