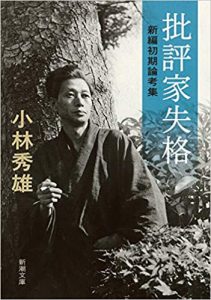歯医者では受付で「非接触おでこ検温」される。先週のこと。「今日はちょっと高いですね」「何℃ですか?」「37.2℃です」「急ぎ足で来ましたからね」と言って手指をアルコールで消毒。この体温で治療が拒否されることはない。
「暑中お見舞い」「残暑お見舞い」の葉書はありがたいが、水色の紙面に金魚や風鈴があしらわれていても、体感温度が1℃上がる。挨拶代わりの「今日も暑いですねぇ」の先制攻撃には2℃上昇。「うだるような暑さ」と言うアナウンサーの声だと一気に3℃!
ゆっくり歩くときついので、速足で一目散に歩く。アスファルトを避けて地下に潜る。何も見たくない、何も感じたくない。必然、視野角が狭くなり感受性も鈍る。中国の古い格言に「暑さの厳しい所から偉人は出ない」というのがある。ひどい偏見だと思う一方で、暑い➔頭を使わない➔賢くならない……と短絡的に連想して危うく同意するところだった。アフリカ諸国と昵懇の仲を保ち続けたい今の中国なら、決して口にすることはないだろう。
暑という漢字は「日」と「者」でできている。日は太陽を表わす。者は人のことではなく、「煮る」の煮の元になった字である。太陽が強く照りつけて、まるで煮えるような熱を帯びている状態そのものだ。こう書いているうちに、再び体感温度が上がってきた。
『歳時記百話』(高橋睦郎著)の夏のページをめくっていたら、まさかの「暑」の見出しがあった。次の文は夏という漢字に言及して書かれた箇所。
『日本国語大辞典』は八語言説を列記するが、最初にアツ(暑)の転、アツ(温)の義、アツ(熱)の義を挙げ、二にアナアツ(噫暑)の義、三にネツ(熱)と通ずるか、という。語源としての当否はともかく、夏は暑いという実感が説の根拠だろう。関連の季語には暑さ、大暑、極暑、溽暑、炎暑などがある。
このくだりを読んで、漢字の凄みが伝わってきた。訓読みすると、噫は「おくび」であり、溽は「むしあつ(い)」だそうだ。読んでいるうちに窒息しそうなほど息苦しくなってきた。マスクのせいばかりではなさそうだ。