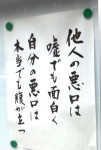「朝が来ない夜はない」だったか「明けない夜はない」だったか忘れたが、若い頃にずっとそう言っていた知人男性がいる。熟年を迎えてさすがに言わなくなったが、明日がやって来ることを前提にした今日の生き方は相変わらずで、身体の隅々にまで楽観が滲み込んでいるかのようだ。これまで生きてきた……よろしい。今日生きている……よろしい。しかし、「明日も生きる」は現実ではない。だから、ぼくたちは「だろう」という未来形で望みをつないでいる。
先月アリストテレス哲学について書いたが、幸福や善について語ると、なんと悠長なとつぶやかれる。幸福も善もプラトンのイデアと同類で、ともすれば明日に結びついてしまう。「明日、幸せに生きるだろう」とか「明日、善を尽くすだろう」などは虚言を弄するに等しい。そうではなく、今日生きている中で幸福と善を実感することに謙虚でなければならない。
ぼくたちはみんな今夜寝て翌朝に目を覚ますつもりでいる。今を生きる、ゆえに明日以降に命をつなぐことを”サバイバル”と呼ぶ。サバイバルは将来に及ぶ話だが、とりあえず「今を生きる」のが先である。「明日などない」と言えば場を興ざめさせるし、いつの時代も評判のよくない意見だが、必ずしも冷淡な発言でもない。なぜなら、明日に希望をつなぐ時点で往々にして今日がおざなりになっているからだ。幸福や善は現在進行形として体感に努めるしかないのである。
青島幸男作詞で一世を風靡し、今も集団でよく歌われるあの歌を思い出す。
♪ 明日がある 明日がある 明日があるさ
残念な今日の自分を励ますのがこのフレーズだ。残念な自分とは、「今日も待ちぼうけ」して「だまって見てるボク」で、「今日はもうやめた」と言い「(電話に)出るまで待てぬボク」、そして「とうとう言えぬボク」が「わかってくれるだろう」と甘える……そんな自分の逃げ場として、「♪ 明日がある……」が6番まで歌い上げられるのである。
モラトリアムもはなはだしい。ただ明日があると信じるだけであって、そこにはダメだった今日の反省も改善策もないのである。あの知人男性一人の話ではない。今日とつながっている明日ならともかく、今日と断絶させておきながら、明日に淡い期待を寄せる人々や集団がおびただしい。懲りない彼らは明日になったら同じことを言うのだ、「♪ 明日がある 明日がある 明日があるさ」と。
「明日があるさ」で思い浮かぶのが「やればできる」である。為末大がつぶやいて賛否両論渦巻いて話題になった。わが国では努力や継続や頑張りの悪口を言うと少なからぬバッシングを受けるのだ。今日の善を実践していない偽善的道徳論者ほどうるさく文句を言う。
冷静に考えてみればわかる。「やればできる」というのは一つの定言命題ではなく、二つの命題がくっついた仮言命題なのである。「もしきみがやれば(P)、それが可能になる(Q)」と言っているのだから、仮定条件のPに軸足がある。勝手にQが実現することはなく、QはつねにPに寄り掛かっている。要するに、「やれば」の「やる」が、誰でもやれるわけではないのだ。才能や経験もさることながら、今日きちんと予定したことをやらねばならないのである。「やればできる」と「明日があるさ」は発想上似通っており、一方が好きな者はほぼ他方も好む傾向がある。