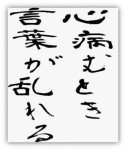今でこそEUのお荷物的存在のギリシアだが、古代は思想、芸術、科学、都市、文化、スポーツなど万般において花盛りであった。今から二千数百年前の話である。東洋の古代思想界もギリシア同様に百花繚乱であった。これ以降の人類が、技術に実績を残してきたものの、知的進化、とりわけ人間性の鍛錬においてどれほどのことを成し遂げてきたのか、大いに懐疑しなければならないだろう。試みに東西を代表する哲学者・思想家を生年順に置いてみた。錚々たる顔ぶれをこうして並べてみると、末席のアリストテレスや孟子が若く見えてくるから不思議だ。
ピタゴラス (前582年~496年)
孔子 (前552年~479年)
ソクラテス (前469年~399年)
釈迦 (前463年~383年)
プラトン (前427年~347年)
アリストテレス (前384年~322年)
孟子 (前372年~289年)

アリストテレスの『哲学のすすめ』の第四章と第五章では「技術」が一つのキーワードになる。目覚ましく進展する技術を開発当事者が持て余し気味の現代社会。アリストテレスの示唆にヒントがあるかもしれない。
技術によって生じるものはすべて、何かのために生じるのであり、この何かは技術にとっての最善の目的である。これに対して、偶運によって生じるものは、何かのために生じることはない。
最先端技術を駆使したドローンは「何か」のために開発された。その何かは元々攻撃や偵察であった。では、攻撃や偵察は最先端技術の最善の目的であるのか……こんなふうに考えてみる。いや、違う。誰の手でも制御できるように小型化した時点で、善用されるべき目的――普遍的な目的――を明確にすべきだったのである。意義深い目的のために開発されたものであっても、濫用に到れば偶然の産物と化す。偶然の産物に善なるものもあるだろうが、理知が働くことは稀である。アリストテレスは続ける……「技術は自然を補助し、自然がやり残したことを埋め合わせるためにあるのだ」。
第六章と第七章。これまでの繰り返しに近い内容である。もっとも、アリストテレスがこの一冊をこの順で書き下ろしたのではなく、「哲学・知識・知性・善」などを主題として断片メモを後世の人間が編纂したのであるからやむをえない。
「知る能力や知識を持ち合わせること」は必要である。しかし、これは可能性または潜在性のものであって、理知的であると言うには不十分である。「知識を用いること」が真の理知であり、現実性を帯びて顕在してはじめて必要十分となる。たとえば健康を目指して学ぶ健康の知識や摂取するサプリメントは可能性に過ぎない。健康になることそのものがより高位の善なのである。実践の知は読書よりも、また、幸せな現実の生活はインフラよりも、それぞれいっそう善に近く尊いのである。
哲学書を読むことよりも、哲学する日々の生活に意味がある。考えることは特別なものではなく、身近であり愉快であること、衒学的な知を格納するのではなく、生活の知としてユーモアを交えて楽しむこと……こんなふうに『哲学のすすめ』の着地点をぼくなりに定めた次第である。最後にアリストテレスのことばで締めくくっておくことにする。
「哲学することは幸福に深いかかわりをもつ」
「最も支配的なものは卓越性〔理知〕であり、すべてのものの中で最も楽しいものである」
《完》
-150x120.jpg)