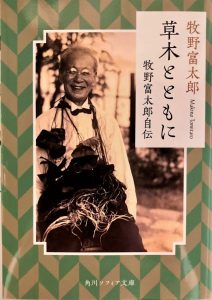「多々益々弁ず」の意味を正しく知っている人は少なく、ほとんどが知らないか誤って解釈している。誤って解釈するのは少々教養があるためで、弁術や弁論に使われる弁という漢字から連想して「話すこと言うべきことが増えれば増えるほど弁が冴えてくる」という意味に解してしまう。
実際、ぼくもそんな一人だった。いちいち辞書を引かなかった若い頃、初見の表現や成句なのに適当に類推だけで済ませて、我流の解釈のままで放置していた。その最たる例がこの「多々益々弁ず」。ある日、この表現が弁論に関わるものではないことを知る。さすがに今は、分かったつもりにならぬよう、面倒臭くても調べるようにしている。
弁論や弁護の弁は「話す」の意で旧字の「辯」には言が入っている。一方、多々益々弁ずの弁の旧字は「辨」のほうで、「弁える」の意。すべきこととそうでないことの区別やけじめをつけて、物事を巧みにコントロールしたりマネジメントしたりすることだ。多々益々弁ずは「仕事や物事が多ければ多いほど処理能力が高まるさま」を表わしている。
言語や表現が豊かというのではなく、仕事や物事の「事」にまつわる成句なのである。あの人は多々益々弁ずと言えば、仕事や物事が増えても次から次へと片付ける、手腕や能力のある人物のことにほかならない。なお、由来についてはここでは書かないが、たいていの故事名言・諺辞典には記述があるので参照していただきたい。