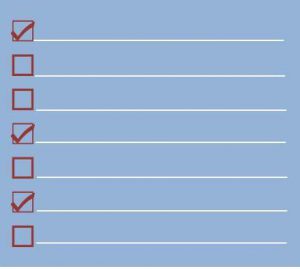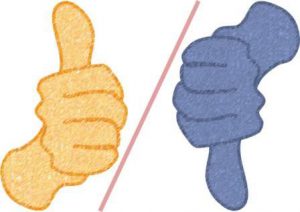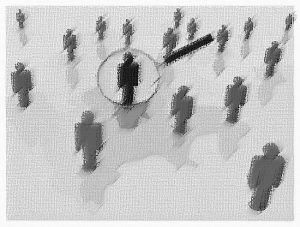仕事柄、企画書をしたためて企業に提案してきた。入札の場合、競合相手がある。競合に勝ち負けは必然。この30年、勝率は8割を超えているから上々の出来である。それでも2割は負けている。勝ち負けが逆になっていたら、たぶんこの仕事の今はなかった。
企画の規模にもよるが、短くても一週間、長ければ一ヵ月近く案を練って準備をする。不幸にして、却下の憂き目に遭うと心中は穏やかではない。しかも、ほとんどの場合、却下の理由は明かされず、またコンペを勝った競合相手の案の優れた点は知らされない。敗因分析しようにも、他の案がわからないので失望をなだめるすべはない。
昨年の今頃、コンペ参加の依頼があった。得意分野の研修テーマの実施計画だったので、余裕綽々、どんな相手でも勝てると踏んでいた。意に反して、結果は負け。研修会社経由の依頼だったので、プレゼンテーションはその会社がおこなった。案は良かったがプレゼンが下手だったと思うことにして、負けを引きずらないようにした。
入札する側を何度も経験し、また入札審査する側にも立つことも多い。審査し合否を決定する側のほうが気楽である。採用案に対しては評価点が最高点だったことを示し、その理由を型通りに告げればいい。しかし、却下された案にはほとんど却下の理由は示されない。数案のうち一案だけが選ばれるわけだから、却下された他の案には「ダメでした」という結果さえ伝えれば済む。
『まことに残念ですが……』という本がある。「不朽の名作への不採用通知160選」という副題が付いている。現在超名作とされている錚々たる小説が、書かれた当初は出版社に拒絶されていた。その不採用の旨を作家に送った手紙が収録された本だ。
「まことに残念ですが、アメリカの読者は中国のことなど一切興味がありません。」
『大地』を書いたパール・バックはこのように告げられた。本のタイトルとなった、「まことに残念ですが……」とあるだけでもまだましなほうである。
アンネ・フランクの『アンネの日記』の場合はこうだ。
「この少女は、作品を単なる“好奇心”以上のレベルに高めるための、特別な観察力や感受性に欠けているように思われます。」
『タイム・マシン』でH.G.ウェルズは次のようにこき下ろされた。
「(……)たいして将来性のない、マイナーな作家だ。この作品は、一般読者には、おもしろくなく、科学的知識のある者にはもの足りない。」
却下する側の気楽さが窺え、却下された側のやるせない思いが伝わってくる。人が他人を評価するとはこういうことなのである。ある人間の評価と世間一般の評価が同じであるはずもない。諾否を決める評価者が人それぞれの基準を持っているのは当然のことである。
しかし、今から見れば理不尽かつ滑稽な断り状だとしても、これらの不採用通知には理由が書いてあった。理由があれば、それを読んで絶望すると同時に、立ち上がる勇気の種も手に入れることができるかもしれない。“No!”の言いっ放しで済ませている当世コンペ実施側の良識と応募者への敬意はどうなっているのか。切に問う次第である。