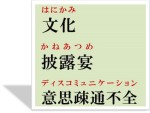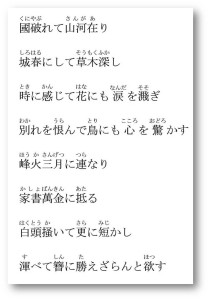ぼくの英語遍歴――。
中高生の時代、英語は得意科目の一つだったが、所詮与えられたものを記憶して点を取ったに過ぎない。自発的に学ぶ対象を決めて独学し始めたのは19歳の時。毎日数時間ひたすら音読した。学びの身でありながら、指導する側に回るのが手っ取り早いと考え、21歳から英会話学校で英語を教え始めた。
二十代後半から英語を使う国際広報の仕事に就いたので、28歳を最後に英語の勉強をやめた。仕事上でアウトプットすることが必然になり、使えば使うほど新たなインプットを促すことになったから、もはや学習の必要がなくなったのである。
さて、日本の英語教育。原則、義務教育の7年目から本格的に英語を学ぶことになっている。高校でも学ぶので、好き嫌いを問わず、また習得度のいかんにかかわらず、ほとんどの人が6年間授業を受けることになる。教えた経験から言うと、誰もが英語を習得できるようにはならない。何をもって習得とするかは本人次第だが、習得という満足を得られるのはつねに少数派である。他の習い事とは比較にならないほど習得率が低く、百人に一人どころではないほどの狭き門と言ってもよい。
だが、英語学習のゴールや結果が必ずしも習得である必要はない、とぼくは考えている。母語だけで生涯を過ごすのに比べて、ある時期に英語に触れれば日本語のコミュニケーションに深みと妙を加えるきっかけになるからだ。だから、いろんな意見があるだろうが、十代に6年間英語に触れることに意味無しとは思わない。一方が母語である日本語で、他方が拙い英語であっても、二つの言語で表現や概念を知れば世界観が広がるのは間違いない。
漢字の字源や由来を知ると楽しい。同様に、英語や他の言語の語源も、調べ始めると興味が尽きない。
実は、ラテン語も独学したことがある。言うまでもないが、ほぼ死語であるラテン語を誰かと話そうなどという魂胆があるはずもなく、また、習得してラテン語の古い本を読もうという野望があったわけでもない。ラテン語を少し齧っておけば、現代のイタリア語や英語やフランス語の表現に親近感が持てそうな気がしたからである。
つい最近も古本屋で『ことばのロマンス』という本を買った。この種の本は他人に薀蓄する以外に役立ちそうもないし、数ヵ国語の現代語・中世語・古代語を行き来するから、読むのが少々面倒である。それでも、遊び心で拾い読みしてみるのだ。語源に興味を持てば、語彙の「体幹」がしっかりしてくるような気がしてくるのである。
Skirt(スカート)という英語がある。これは北欧起源という。このことばの二重語にshirt(シャツ)がある。ちなみに、二重語とは同じ起源を持つ二つの単語のこと。つまり、英語のスカートとシャツは根が同じというわけ。では、根はどこか。俗ラテン語のex-curtusである。意味は「短い」だと聞いて驚く。短いは英語でshortだ。そうか、道理でskirt、shirt、shortは酷似している。何のことはない、わざわざ「ミニスカート」などと言わなくても、元々スカートそのものが短かったのである。
英語にjiltということばがある。手元の辞書によると、「〈気をもたせたり婚約したりした後で、女が恋人を〉捨てる」という意味の動詞である。名詞ではずばり「男たらし、浮気女」。英語の古い形ではjilletで、女性の愛称Jill(ジル)も同じ。JillはJuliana(ジュリアナ)の短縮形だ。そして、かのシェークスピア作中のJuliet(ジュリエット)がこれの二重語。そう、ジュリエットは語源的に男たらしだったのである。スカートの語源とジュリアナの語源を足し算すれば、1990年代のジュリアナ東京のああでなくてはならなかった理由が見えてきそうだ。