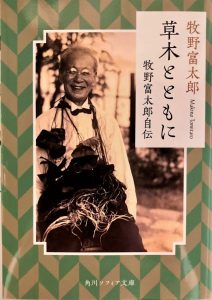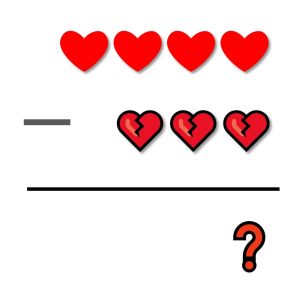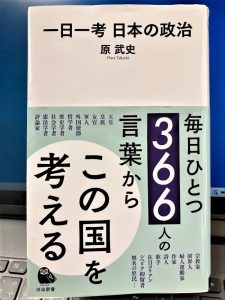2008年3月、ミラノの「レオナルド・ダ・ヴィンチ記念国立科学技術博物館」にいた。一巡して中庭で休んでいたら、現地の社会見学の少年たち数人が近づいてきて「日本人か?」と聞く。うなずくと、一人の少年が別の少年を後ろ向きにしてTシャツの背中を見せた。
「これは日本語?」と聞くから「そうだ」と答えたら、どんな意味か教えろと言う。イタリア語では小学校高学年以上の少年は“ラガッツォ”という。対して、幼い男の子は“バンビーノ”だ。彼らは14、5歳なのでラガッツォがふさわしいが、それではおもしろくないので、バンビーノと言ってやった。案の定、Tシャツ少年はみんなに背中を指差され、「バンビーノ! バンビーノ!」としばらくからかわれていた。
胸にベートーベンのイラストが描かれているTシャツを見たことがある。背中を見るとトンカチを手にしたベートーベンの別のイラスト。意味があるのかないのか、あるとすれば解くべき謎があるのか。背中のイラスト、そのココロは「大工=第九」だった。
少年もベートーベンのTシャツも特殊なギャグで、一般汎用的にピンときたり笑えたりするものではない。漢字を読めないイタリア人にとっては「少年」と書かれたTシャツに意味はないが、バンビーノと訳せば少年が坊やになるから冷やかしネタになる。ベートーベンのほうは日本限定のローカルギャグ。しかし、第九を知らない日本人には通用しない。
所詮ローカルなネタなのだから、Tシャツはベートーベンではなく、千利休や幕末人気人物ナンバーワンの坂本龍馬あたりにして、何か工夫をするほうがいいかもしれない。高知では映画『ローマの休日』をもじった「リョーマの休日」という観光キャンペーンが展開されている。
阪神タイガースで活躍したランディ・バースが入浴シーンのコマーシャルに起用されたことがある。バースから「バス=風呂」を思いついたのだ。バースは“Bass”と綴る。風呂のバスは“bath”である。文字でも発音でもまったく類似性のない、別物である。時代が下って、阪神ではマートンが活躍した。マートンは“Murton”と綴り、発音は口を開いた「マー」ではなく、口を閉じ気味に鼻で「ムー」と響かせる感じだ。なのに、応援席ではファミリーマート(Family Mart)と絡ませた「ファミリーマートン」という文字が揺れていた。
上記の例は英語のダジャレではなく、ローカルなカタカナ遊びにすぎない。ダジャレの国際化は実に難しいのである。世界に通じるユーモアを目指すなら、地域文化を脱してユニバーサルな価値をネタにする必要がある。